http://lamplight.ho-zuki.com/ [灯火]
MOON STONE 後編
ほぼ那翔オンリー。R-15。
大丈夫な方のみ、ご覧ください。
↓スクロールしてね↓
「んで、お前いつ連休取れる?」
「ええと…しばらくは難しそうです…1日だけ、とかなら大丈夫なんですが2日間は…」
「生放送終わってからいきなりオファー増えてきたしなぁ。俺もしばらくは無理そう」
「視聴率よかったみたいですしねえ」
以前、月1の生放送番組、シャイニング☆オールスターで俺は2位を取って遊園地のペア招待券をもらった。
本当はレンとペアを組んでたから、レンと行くことになるのかなーと漠然と考えてたら、ちょうどその生放送が俺と那月の誕生日で、俺と那月の仲がレンにバレてしまったのもあってレンはその招待券をプレゼントしてくれたんだ。
ペア招待券はスイートルーム付きの1泊2日で、俺たちはその予定をどこに入れるか考えていた。
と言っても、招待券に書かれた注意書きを読んでみると事務所特注の招待券なのか、それはナイトパスポートと同じで夕方から入れるもので、スイートルームも昼前にはチェックアウトという、のんびりする間もないものだった。
俺たちのことは社長と春歌、そしてレンの3人しか知らなくても、マネージャーは俺たちが友人として仲がいいことを知ってるから、同じ日に休みをとっても変な目で見られるようなことはない。那月のマネージャーはむしろ、その発想に至る人柄ではないと言った方がいいのか、かなりフレンドリーに接してくれるし、反対に俺のマネージャーはあまり人に干渉することをよしとしない人だったから、特に詮索されるようなことはなかった。
それに、番組内でペア招待券をもらったとき、那月が言った「えー僕も行きたいです!」に「じゃあ、シノミーは自腹でついてくるといいよ」なんてレンが冗談めかせて言っていたし、レンなら遊園地のことじゃなくても詮索されたら上手い具合にフォローしてくれると思うから、その辺は安心している。
「合同ライブも入ってるし…空きが出来てもレッスンしときたいからなぁ」
2人してソファに座りながら、スケジュール帳を見て、息をつく。
「僕も7月にミュージカルがあるし…ふふっ、嬉しい悲鳴と言うやつですね」
「そうだなーデビュー前なんか真っ白だったんだから、やっぱ嬉しいな」
デビュー前もレッスンやコンペ応募、オーディションなんかも受けてたから忙しくはあったけど、確定している予定でこんなに埋まっているのを見ると自然と笑顔になるというものだ。
招待券の期限は7月末まであるから、俺たちはマネージャーに相談することにした。
那月のミュージカルの千秋楽を迎えて数日経った7月末に、俺たちはマネージャーに調整してもらったオフに遊園地へやってきた。梅雨も終わり、強くなってきた日差しが眩しいほどの晴天だった。
招待券はナイトパスポートだから、夕方5時から入れるようになる。それまで、近くにある海に面したレストランで食事をしたり、ウィンドウショッピングをしたりしながら過ごした。そして、時間が迫ってくると、先にホテルにチェックインだけ済ませておいた。
変装のために俺は縁が大きめの赤い伊達メガネと、普段メディアであまり被らないキャスケット帽子を被り、那月は度入りのサングラスを掛けてきた。
遊園地に入って那月が真っ先に向かったのは、お菓子の国をモチーフにしたお菓子風の建物が並ぶ一角。淡い色使いで、のっぺりとしても見える建物に囲まれた、中央広場の噴水に、その奥にあるお城もまたお菓子風で作られている。
前にも那月とこの遊園地に来たことがあって、その時は女装させられてたからそんなに視線を感じなかったけど、こんなメルヘンな場所に男2人で来たせいか、やたらと視線が気になった。
だからと言って、女装したくはないけど…もしかしてバレたとか?
「おいこら、あんまはしゃぐなって」
くるっと振り返った那月が俺の方に駆け寄ってくる。
そして、那月が掛けているスポーツサングラスを見て、視線を感じる原因がすぐに那月にあるのだと分かった。
「っ…あはは…お前、それやっぱ似合わねえな」
かわいいだの、あれ見てだのとはしゃぐ那月の言動と、身長が高いのもあってスポーツサングラスを掛けた見た目とのギャップが凄まじい。
日食を見たときも、那月はやたらとかっこよさげな日食グラスを掛けてるのに、言動と合わなくて爆笑したんだよな。
「ええ?選んでくれたの翔ちゃんですよぉ〜?」
「そうだけど…黙ってれば似合うのになー」
那月がサングラスをずらして顔を覗き込んでくる。
「かっこいい?」
「…黙ってればな!」
「ふふっ翔ちゃんは今日も可愛いですよぉ!」
「ハイハイ。可愛くねーよ」
気分がよくないのは間違いないけど、毎日言われすぎてムキになって否定することは減ってきていた。
ファンにも言われるし、どう頑張っても見た目のせいか「可愛い」から抜け出せないらしい。
せめて170cmはほしいなんて夢見てたけど、現実は学園の頃からそんなに変わらねえし、逆に那月に撫でられるたびに縮まってんじゃないかと思うほどだ。
「ねえねえ、翔ちゃん!」
那月があるものを見つけた途端、腕をぐいっと引っ張られる。
「なんだ?コスプレはしねえぞ?」
那月の視線の先はこの遊園地のキャラクターの衣装に着替えて記念撮影が出来るコーナーだった。
こういうのは大抵、女装させようとしてくるのが那月のお決まりだ。
「絶対可愛いのに…!」
「お前の目は節穴だ!とにかく、違うとこ行こうぜ」
那月の腕を引っ張って、そのコーナーから逃げるように歩いていく。
かと言って、城の中にはビスケットやクレープなんかのお菓子の手作り体験があって、那月を連れて行くのは危険だし、ここは子ども用の広場みたいなものだから、アトラクションと言えばオレンジやレモンなどの皮で出来たコーヒーカップ、一般的なキラキラした飴細工ではなく、屋台なんかにある手作りの飴細工のような少しだけいびつなところがある白っぽい馬やウサギなどが回っているメリーゴーランドぐらいしかない。
前に着た時は女装してたから恥ずかしくてもなんとか耐えられたけど、今日は絶対に乗りたくなかった。
「翔ちゃん歩くの早いよ〜何か乗りたいのあった?」
「そういうわけじゃねえんだけど…そうだな、ジェットコースターに乗ろうぜ!」
お菓子の一角からは離れた、緑や花がたくさん植えられているところにあるジェットコースター。それは一般的によくある回転するものだ。
ヒーローショーも燃えるけど、ジェットコースターはアトラクションに乗ってる!って感じがして好きだ。
「うん!行こう!」
今度は那月に手を取られて、スキップ気味にジェットコースターへ向かう。俺はただ引っ張られてるだけだけど、腕をぶんぶんと振られてしまう。
そして、那月は俺たちのデュエット曲である、GO!×2ジェットコースターをアレンジしながら鼻歌で歌い始める。元々明るく転調が多めのポップな曲調が、全体的にテンポダウンして伸び伸びとした曲になっていた。穏やかなビブラートを多用して、時折俺の方を振り返って微笑む。
那月の歌は誰よりも感情が乗りやすいと思う。悪く言えば気分屋であるそれは、今の那月の表現したいことが全て歌に乗るということ。表現し切れなくて悩むことも多いようだけど、それでも少しずつ変化して歌声の芯が強くなっている。
クラッシックでは那月に適わないと思って諦めたけど、今は諦めるどころか、那月の才能が羨ましいと思うと同時に俺を奮い立たせてくれる最高のライバルなんだって嬉しかった。
俺も那月にとって、そうで在れるように頑張らないとな!
那月の鼻歌に小声で歌詞を乗せてやれば、那月は微笑んで言の葉に切り替える。
掛け合いが終わるころ、ちょうどジェットコースターの前までたどり着いた。
待ち時間は40分と短めで、最後尾に並びながら那月に声をかける。
「そういや、飯時か…ただ待ってるだけでもアレだし、あそこのワゴンで何か買ってくるけど、お前なんか要る?」
少し遠くにあるワゴンカーで売られているのは主にクレープやポップコーン、夏らしいソフトクリームにカキ氷なんかが中心で、フランクフルトや菓子パンも並んでいる。
「え、僕も行きたい!」
「言うと思った。でも、2人しか居ないんだからどっちかが並んどかないとなんねーし、お前すぐ迷子になるから」
那月は理数系に特化して頭がいいはずなのに、道は覚えられないのか、それとも色んなものに気を取られていつの間にか迷っているパターンなのかは分からないけど、結構な方向音痴だ。
ワゴンは目と鼻の先でジェットコースターが見えているし、看板も立っているとは言っても、ここは遊園地内だから那月にとって目を引かれるものはそこかしこにある。
「うーん…そうですね…」
しょんぼりする那月を見て、ふうと息を吐く。
「分かった。後で一緒に行こうぜ。先になんか食って気分悪くなっても困るからな」
ちょうど近くを通ったジェットーコースターに周りから歓声が沸く。
「はぁい!楽しみです〜」
那月とジェットコースターを眺めながら、仕事で一緒になった同期のメンバーの話をして順番を待った。
那月と無事にジェットコースターを乗り終えたとき、辺りはもう暗くなっていて携帯電話の時計を見ると7時半を回っていた。
ジェットコースターに乗っている間、那月はずっと笑いが耐えなくて、俺もつられて叫ぶように笑い声を上げていた。
外ではアイドルだってバレないように気をつけてるから、あんまり大きな声を出すことはないけど、ライブで叫んだときのようなすっきりした開放感があって、ジェットコースターのわくわくだけじゃなくて、そっちの意味でも楽しめた。
そして、乗っているときに記念として機械に撮られた写真がスクリーンに映し出されてて、帽子やストールを外してたのもあって、分かる人にはわかるのかちょっとした騒ぎになってるのに気づいて、俺たちは隠れるようにしてその場から逃げた。
「俺、自分の知名度舐めてた」
シャイニング事務所というだけで注目してくれる人はたくさん居る。でも、覚えてくれるかどうかは別問題だから。
「はい。でも、気づいてもらえて嬉しいって思っちゃいました」
「あぁ。自分の目で見て実感することも、プロ意識を高めるのに最適だよな」
騒ぎにならないようにって思う半面、どれぐらい俺のことを知ってる人が居るんだろうって気になるのは仕方ない。
「あーでも、あれじゃあ、しばらくワゴンんとこ戻れねーな。どっか入るか」
パンフレットに載っている地図を見ながら、レストランのマークを探す。
「僕ここがいいなぁ」
那月が指差したところは半個室のレストランだった。
落ち着いた雰囲気の橙色の照明、ダークブラウンの家具が置かれた店内の写真が載っている。
そうして、俺たちは那月が選んだレストランにやってきた。
用意されたテーブルに腰掛ければ、店員がカーテンを閉めていく。
窓がない壁際を頼んだのもあって、誰かにバレる心配はぐっと減った。
「同じ遊園地にお菓子の国があるとは思えない店だなー」
それに遊園地はどこも混雑するから、流れ作業のように注文するカウンターでオープンカフェのような店が多くて、まさに隠れ家のようなところだった。
「翔ちゃんこういう雰囲気のいいお店好きでしょう?」
「え?あぁ…」
帽子を外しながら曖昧に答えてみせる。
ファミレスだって、慌しい食堂だって好きだ。でも、こういう落ち着いた店は那月を連想するから。
よく雑貨屋に行く那月は可愛らしいイメージが強いけど、カフェで紅茶を飲みながら話をする時間も同じぐらい多くて、那月の大きな腕で抱きしめられているときのような安心感がある。
それに半個室自体が周りは見えないし、見られないから落ち着ける。
「ふふっ僕も好きですよぉ」
那月はメニューを一度見てからすぐにサングラスを取って、いつものシルバーのフレームのメガネを掛ける。
サングラスをテーブルの端に置きながら那月はため息をついた。
「…サングラスさんは文字が見辛いのが困ります」
「もう外も暗いし、それでいいと思うぞ。危ないしな」
メニューに視線を落として、どれが美味そうかな、とページを捲っていく。
洋食を基本とした一般的なメニューが揃っていて、ここの店はスパゲッティを多く取り扱っていた。
よし、多めのクリームソースに温泉卵が乗ったカルボナーラにしようかな。
「俺はカルボナーラな。那月は決まったかー?」
「翔ちゃん翔ちゃん!」
「ん?」
顔を上げれば、ちょいちょいと手招きする手につられて、那月の方のメニューに顔を覗かせると、すっと俺が掛けている伊達メガネを取られてしまう。
那月が僅かに首を傾げて微笑みながら、俺の髪を撫でてくるから苦笑する。
「なぁんだよ?」
「やっと翔ちゃんのお顔をちゃんと見られたなぁって」
そんな嬉しそうな顔で面と向かって言われて思わず目を逸らせば、ふっと顔が近づいてきてキスされてしまう。驚いて目を見開けば、那月がじっと俺の目を見てくるから、合わせられなくて伏せるだけだった。舌を重ねられて鼓動が早くなってきて、顔まで熱い。誰に見られるか分からないから、早く離れないとと思うのに、那月を強く押し返せない。
そのまま流されてテーブルに乗り上げるように手を着いて、那月の頬に手を添える。舌先を那月に吸われて、小さく声が漏れた。
「ん……ぁ…」
あぁ、ダメだこれ以上したら。
「失礼します」
そう思った瞬間、聞こえてきた声に驚いて、慌てて飛びのいてさっと座る。
「お冷、お持ちしました」
店員に顔を見られないように、俯きがちでいるしかなかった。
絶対、真っ赤だし…あぁ…。
「ご注文はお決まりですか?」
「まだです〜」
「お決まりになりましたら、そちらのボタンでお呼びくださいね」
那月が暢気に返事をすると、店員がカーテンを閉めて去っていく。
「アホか!こんな、とこで!」
小さく叫べば、那月は満面の笑みを浮かべて言った。
「ふふっ、翔ちゃんも返してくれてうれしかったです」
「〜〜〜っ!」
引力でもあったんじゃないかって錯覚するぐらい那月に強く惹かれることはあるけど、最近特にそうなってる気がして耳まで熱くなる。
「…かわいい」
「いいから、早く何食うか決めろっ!」
伊達メガネを掛けなおして、メニューをとんとんと叩く。
「う〜〜ん、翔ちゃんはミートスパゲッティとたらこのスパゲッティ、どっちがいい?」
那月はいつもメニューをなかなか決められない。あれもこれもと食べたがるから、お互い別のものを頼んで少しだけ交換するというのが習慣づいてしまっている。
だからか、決められない那月の代わりに俺が決めるようなもんだった。
「ミートかな…」
たらこでもいいけど、俺のカルボナーラには卵が乗ってるから。
「あぁ、お前カルボナーラでいいのか?別にミートとたらこでもいいぜ」
「ううん。翔ちゃんのも食べたいって思ってたから。それじゃあ、ウエイトレスさん呼びますね〜」
そうして、注文したカルボナーラとミートスパゲッティは遊園地内のレストランということもあってあんまり期待していなかったけど、思っていたよりも美味しかった。
「パレードは8時30分からだから…」
那月はパンフレットを覗きながら最後の一口を口に運ぶ。
「間近で見るのもいいですけど、観覧車から見てみたいなぁってずっと思ってたんです」
「ふーん?8時回ったとこだし観覧車んとこ行ってみるか。今から乗る人は流石に少ないだろ」
テーブルに置かれている紙を取って、ミートソースがついている那月の口元を拭ってやる。
「…ほら、ついてる」
「ありがとう」
「って、何で俺がやってやってんだよ…もう癖か」
思わず音也の前とかで同じことをやったときも、この程度なら世話を焼いてるだけに見えるのか「那月って翔の弟みたい」なんて流されたっけ。
「翔ちゃんが僕に世話を焼いてくれるのが嬉しくってつい…」
「な〜に〜?お前わざとだったのか!」
「どうでしょう…?でも、翔ちゃんがすぐ気づいてくれるのってすごいなぁって思うんです。だから、僕も翔ちゃんのことを誰よりも先に気づきたいなっていっつも思ってるんですよ〜」
「……話を逸らすな!」
ピアスを変えたときも同じことを言われたけど、照れてしまう俺はやっぱり単純らしい。
でも、那月のことだから天然なのか、わざとなのかよく分からない。
ちゃんと考えてるんだなーって思うことはあるけど、いつ見てもマイペースで我が道を進む那月は周りに染まらない独自の世界観があって、それに振り回されるのも悪くないって、最終的には天然でもわざとでも那月なら何でもいいんだと思えた。
那月と繋いでいた手の感触が残っていて、手の平と目前の人の塊を交互に見ながらため息を吐いた。
観覧車に乗ろうと那月とそこへ向かっている途中で、パレードを見に集まってきたたくさんの人に那月と手を繋いでいたのにもかかわらず、俺たちははぐれてしまったのだ。
俺だけが人の波に流されて放り出されたに近い。下手に動かずに近くのベンチに腰掛けて、携帯電話で那月に電話を掛ける。
「翔ちゃんどこ!?大丈夫!?」
ワンコールで通話が始まり、慌てた様子の那月の声が飛び込んでくる。
「あぁ…今は少し離れたとこのベンチ」
傍にあったアトラクションの待機時間が掲載されているボードを見上げる。
そこにはナイトパレード20:30〜と書かれていて、現在の時間は20:18になっていた。
たぶん、那月が見たがってたのはパレードもそうだけど、開始と同時に打ち上げられる花火だ。那月が観覧車でパレードを見たいって言ったとき、花火を間近で見るために乗りたがっていたんだろうと察しはついていた。観覧車の時間は15分程度で7分もすれば頂上だから、急げば間に合うはず。
そう思って立ち上がり、少し遠くにある観覧車に向かって走りだす。
「お前は平気か?観覧車が近いんなら――」
そこ行って待ってろ、そう言いかけたとき、通話がブツッと切れてしまう。
何かあったのかと、慌てて電話を掛けなおしても通じなかった。
「マジかよ…」
日が沈んだとはいえ、もう7月末で空気自体が暑いのもあって、携帯電話を握る手が汗ばむ。
迷子センターか何かで呼び出しても、那月が来られるとは思えなかった。
中で砂月が起きてて、道を覚えてればあるいは…。
「いや、先に観覧車行ってみるか」
那月と違って砂月は方向音痴ではないから、迷子になった那月は俺に電話を掛けてくるか、砂月を頼ることがある。だとするなら、慌てていた那月を落ち着かせて観覧車に行けと言ってくれるはず。
もうパレードが目前に迫っていて人だかりが増えている。
それをすり抜けるように端を小走りに進んで、ついでに那月が居ないか辺りを見回してみるけど、なかなか見つけられなかった。
少し離れたベンチ、そう伝えてしまったせいで那月も俺を探しに動いているかもしれなくて、すれ違ってたらと思うと不安で、早く那月に会いたくて観覧車の前までたどり着くのにそんなに時間は掛からなかった。
俺の考えていた通り、観覧車に並んでいる人はあまりいない。
でも、そこに那月の姿はなかった。
立ち止まったせいで一気に汗が噴出してきて、帽子を取って服をぱたつかせる。
息を吐いて、もう一度那月に電話を掛けてみるけど、やっぱり繋がらない。
待ってれば来るかもしれない。
そう思って、しばらく待ってみても一向に那月は現れなくて、ついにはパレードが始まると共に星が煌き始めた暗闇の空に大きな花火が打ち上げられる。
「あぁ…」
もっとちゃんと手を握っておけばよかった。
那月が握る力は強くても、外なのには変わりなくて、俺はあまり自分で力を入れて握ってはいなかったから。
花火やパレードを見つめる人の歓声が響く。きらきらと光るイルミネーションが眩しくて、俺は那月を探しにその場を後にした。
『――つき、どこまで行く気だ!那月!』
頭の中で響く声にはっとした。
「さっちゃ…」
慌てて辺りを見回せば、切れ掛かっている外灯がちかちかと点いては消えを繰り返していて、自分がどこにいるのか分からなかった。
ふと強く握り締めているものに気づいて、手を広げてみる。
ただの四角い機械。ところどころ破損していて、それを開いてみれば画面が割れている。
一瞬、それが何か分からなかった。
「僕、ぼく…」
『―――』
さっちゃんが何か言っている。でも、何も言葉として頭に入ってこなかった。
壊れて何も映らなくなった画面に、手が震えてそれが滑り落ちた。
直後、ゴッという音が耳に痛いぐらいに響いてきて、慌ててそれを拾い上げた。
なんでもいい、画面がついてくれさえすればいい。
そう思って、何度も何度も電源のボタンを押した。
たまに小さなデジタル音が聞こえる程度で、画面がつく気配はなかった。
「ど…しよ…翔ちゃんのめぇ…る…」
翔ちゃんから色んなメールをもらった。でも、もらってから毎日毎日読み返していたメールがある。
それは先月にもらった誕生日メール。
家に帰ったら転送したメールをパソコンから見れる。でも、それは日付が6月9日0時0分じゃない。
そんなデータ上の日付でさえ、固執してしまう。
それぐらい大事だった。翔ちゃんと1番に交換出来たってことが僕の宝物だったんだ。
一度それを手にした以上、手紙にしてもらったらよかったなんてもう思えない。
僕の、わがままだ。
『――出せ…思い出すんだ、那月。メールの内容を、チビの言葉を』
「しょ…ちゃんの言葉…?」
メールの内容は何度も何度も読み返して覚えている。
そして、読み返すたびに聞こえてくるのは翔ちゃんの声だった。
あのとき、翔ちゃんは僕へのメールを打ちながら、一音一音小さく小さく声を出していた。
『那月、誕生日おめでとう。改めてこんなん書くのも恥ずかしいけど約束したからな。ありがたく受け取れ!…とは打ってみたものの、マジで難しいな。こういうときお前なら、すらすら出てくんのかもな』
初めの言葉は僕が居ないときに打っていたのか、聞いていなくて僕の想像上の翔ちゃんの声だ。
それから、目を閉じれば、急いでメールを打っている翔ちゃんの姿が鮮明に浮かぶ。
そして、すんなりと頭に降りてくる翔ちゃんの声。それはリップノイズに近い、とてもとても小さな音。
小鳥さんの声を聞き分けるように、翔ちゃんのリップノイズを頭の中で再生する。
『んーと、まずお前は俺にとってホント手のかかる弟みたいな存在だった。それがいつしか放っとけないのは弟みたいだからってだけじゃないって気づいたんだよな。砂月のこともそうだけど、ほんっとうに色んな意味で目が離せない。でも、ドジるな!なんていくら言ったって、お前が自分でどうにかできるなら悩んだりしねえよな。もうある種、それがお前の個性なんじゃねえかな?って思うこともあるし、那月は那月らしくしてればいいんだよ。フォローならしてやるから、これからも一緒にトップアイドル目指そうぜ!もちろんお前に負けるつもりはねえから、覚悟しとけよ!翔』
うん。翔ちゃんはちゃんと僕を見てくれてる。受け入れてくれてる。
知ってた?僕には翔ちゃんが必要だから、翔ちゃんにも必要だって思ってもらいたくて、僕の歌が音楽が進化し続けるんだよ。少しでも翔ちゃんの先に居られるように。追い越されたら、追いつけるように。そうしたら、ライバルってだけでも僕を必要としてもらえるでしょう?
「うん、もう大丈――」
目を開ければ、真っ先に壊れた携帯電話が飛び込んできて、一気に青ざめた。
それは翔ちゃんと一緒に買いに行った、おそろいの携帯電話。
僕は上手に操作できないから機械が苦手で、たくさんの機能があるやつは間違えて操作しちゃったら戻し方が分からなくなってしまうから嫌だった。でも、翔ちゃんは一番新しい機種を欲しがってて、携帯電話を選ぶ翔ちゃんの楽しそうな顔を見てたらなかなか言い出せなくて。
そうしたら、翔ちゃんが不安になってる僕に気づいて「一番新しい機種だったらおそろいでもカモフラージュになるし、操作がわからねえなら教えてやるから」って言ってくれた。
でも、僕は何度教えてもらっても分からなくて、間違えて操作しちゃったときも翔ちゃんは面倒くさがらずに教えながら直してくれた。絵文字だってまだ1人で使えないけど、この携帯電話にはメールだけじゃなくてそんな思い出がたくさんあるから、それが全部、汚されてしまったようなそんな気持ちになった。
壊れたからって、思い出が消えてなくなってしまったわけじゃない。それは分かってても、こんなに悲しくて辛いのはどうしようもないことで、唇が震えて涙がこみ上げてくる。
『っ……』
さっちゃんが唇をかみ締めてるのが分かって、早く、早く翔ちゃんに会いたかった。
僕を、さっちゃんを、その小さな体でぎゅって抱きしめてほしい。そして、強く抱きしめたい。
僕は無我夢中で遊園地内を走り回った。
汗が零れ落ちてきて目に沁みる。
「那月〜?なーつきー」
大声を出して注目されたら困るから、小さく呼びかけるようにしか声を出せなかった。
那月は身長が高く、帽子を被っていないから余計に目立つオレンジがかったクリーム色のふわふわな髪を頼りに走り回った。
「おーい」
帽子を取って頭を振って、大きく息を吐く。
ここの遊園地のパレードは周回ルートが短くて、その場でずっと見ている人が多いから、人だかりがバラけることがあまりないせいで、目を凝らして探しても那月らしい人は見当たらなかった。
俺は最初に電話をしたときに居たベンチに戻って那月が居ないのを確認して、もう一度観覧車へ向かう。
でも、やっぱり見つからなかった。
普段から那月がいつか車に轢かれるんじゃないかって心配する反面、クマを倒せるやつだから、あの超人的な力でなんとか出来るかもって思ってるのも本当だったから大丈夫だとは思うんだけど、ここまで見つからないと、どこかで怪我でもしてるんじゃないかと思ってしまう。
那月と再会したとき、世間は狭いと思った。でも、こんな遊園地の中でさえ見つけられないのなら、あれは奇跡だったんだと強く思った。
パレードを見ているかもと、その付近ばかりを捜していたけれど、今度は那月が気に入っているお菓子の国の一角に足を向けてみる。
そこに辿り着く前から見るからに人が減っていて、閑散としても見えた。
パレードの辺りはかなり探したから、少しだけ期待していたのも空しく、ここにも那月は居なかった。
迷子センターか医務室にでも行ってみようかと、もと来た道を歩く。
「なつきー」
1日中のレッスンや、ライブに比べたら全然声を出していないのに、掠れた声しか出ない。
周りはカップルや親子連れでみんな楽しそうだから、余計に寂しく感じてしまう。
毎日那月の顔を見てるし、ロケか何かで居ないときもテレビやDVDで見ることもある。電話越しの声だって、CDやiPodに入ってる那月の歌声だって、那月の声を聞かない日はない。
今日だって、朝からずっと一緒に居た。違う、昨日の夜からだ。
なのに、今無性に那月の笑顔が見たい。ただそれだけだった。
つーか、俺すっげえ那月のこと好きなんだな。
そう思ったら苦笑するしかなくて、ため息を吐いた。
近くにあった外灯に背を預けて、空を見上げる。
那月が居ないとき、俺は空を見上げるのが癖になっている。いつも那月が楽しそうに、星一つ一つの説明をして、神話の話をするから、星を見つけるたびに頭の中でそれが反復するように流れてくる。
「那月…」
小さく呟けば、頭の中の那月が返事をするから、また小さく呟いた。
「……好きだ」
「「僕も大好き」」
頭の中で那月の声が2重に聞こえたような気がして、視線を僅かに下げれば、ふっと影が落ちて星が隠れてしまう。星を遮ったのは頭の中に浮かんでいた那月じゃなくて、紛れもなく本物の那月だった。
見つけたら「お前、今までどこに居たんだよ!すっげえ、探したんだからな!」そんな言葉をぶつけるつもりだったのに、那月の瞳からは涙が滲んでいて言葉にならなかった。
直後、何度目かの歓声が遠くで聞こえてきて、花火の音が大きく響いた。
もうパレードが終わるのかもしれない。ということは、そろそろ9時半になるということだ。
1時間と少し。たったそれだけ離れただけで心配というよりは、恋しくなってしまうほど那月のことが好きなんだとまた自覚した。
持っていた帽子を取られて、明るく賑やかなパレードの方をそれで隠して、その大きな体で俺を覆い隠すようにしてキスがやってくる。
――引力。
レストランでも思ったけど、それ以上に強く強く惹かれた。
那月の潤んだ瞳が視線を彷徨わせるから、俺だけを見ろって那月の首に腕を回して縋るようにキスを返せば、腰を支えられてぐっと抱きしめられる。
重ねるだけのキスを何度も交わせば、引き始めていた体温が徐々に上昇する。
那月の髪が汗で濡れているのにも愛しさを感じる。それは那月も必死で俺を探し回ってくれたってことだから。
あぁ、那月の笑顔が見たいのも本当だけど、この存在を感じられるだけで十分だと思った。
「んっ…」
好きだって何度伝えても足りない、学園に通っていた頃、那月がよく言っていた言葉だ。そして、それがどんなに最高の愛の言葉なのか、今はもう知っている。教えてくれたのは那月だ。那月がそう思えるのもこの先、俺だけでありますように、と視界の端に映る花火に願った。
そして、一際明るい花火がふっと消えて、唇から離れれば名残惜しいとばかりに頬にちゅっとキスを落とされる。
那月は僅かに微笑んで、俺の頭に帽子をかぶせてくる。
「…手、ちゃんと繋いでやればよかったって何度も思った。パレードも終わっちまったし…ごめんな」
静かに首を横に振った那月の耳に俺がプレゼントしたイヤリングが光っているのに気づいて、なんとなく気恥ずかしかった。だって、那月の髪が頬に張り付いて耳が隠れてなくて、俺も同じピアスをしてるから、一目でおそろいだって分かってしまう。
パレードが終わって、帰る人のざわついた声が近くまで迫っているのに気づいて、俺は那月を引っ張ってお菓子の国の中央広場にある噴水奥に移動する。
あの混雑の中、ホテルに向かっている途中でまたはぐれたら嫌だから。
ベンチに腰掛ければ、那月は俯いてしまう。
「どっか怪我してないか?」
傷心しているのは見るからに分かるけれど、外傷まであったらどうしようかと思った。
でも、那月は首を横に振るだけで、怪我はしてないようでほっとした。
「……夏祭り連れてってやるから、なんて言っても気休めになんねえか?」
薄暗く光が灯ったお菓子の城を見ながら問いかければ、那月は首を横に振る。
「行きた…い…でも、違うの……携帯…が…」
「…そういや、充電切れたのか?」
途端に、触れていた那月の肩がびくっと震えた。
「…あ、あのね…」
那月がかばんから携帯電話を取り出して、俺に見せてくる。
それは画面の液晶が割れていて、ボタンを押しても反応がなかった。
那月が小さく震えているのが伝わってきて、顔を覗き込めば涙を目にいっぱいためていた。涙を堪えようとしているのか、目が少し充血していて、重みで耐えられなかった涙がメガネにぼたぼたと落ちてしまう。
那月は悲しそうな顔をしても、実際に泣くことは滅多に無くて、俺は那月が泣いているのを数えるほどしか見たことがない。それも、ほとんどが俺絡みなのだから余計に那月が泣いているのを見るのは辛かった。
「……翔ちゃんと選んだ…のに…」
初めはデータがなくなったことで泣いてるのかと思ったけど、那月はいつも大事なメールや画像はパソコンにも送っているから。
「もう買い換えて2年経つよな」
自分の携帯電話を取り出して、壊れてしまった那月のと並べる。
俺のは落ち着いたゴールドで、那月のはピンクゴールド…オレンジがかったピンクだ。
早乙女学園を卒業してから、アイドルとしてのイメージカラーが決まったとき、俺はピンクで那月は黄色だったからそれにちなんで互いの色を交換した。
那月はPIYOちゃんのキーホルダーをつけるから、同じ系統のゴールドよりはちょうどいいってのもあった。
買い換えた当初はおそろいだってことを突っ込まれて、最新のものを選んだだけだ、なんて言い訳してたっけ。
「大事にしてくれてんのは嬉しいけど、お前が泣く方が俺は嫌だ。…そんな泣くっつーことはまた同じの買ってもそれは違うんだろ?」
那月が小さく頷いて、また涙がこぼれてしまう。
「……俺も、買い換えるからさ…また一緒に買いに行こうぜ。言っとくけど、この携帯をどうでもいいって思ってるわけじゃねえからな?お前が泣くぐらいなら、ってこと忘れんなよ」
「うん…うん…しょちゃ……だいすき…」
「ん…ほら、泣き止めって」
肩を抱き寄せてやれば、那月は壊れてしまった携帯電話を大事そうに抱きしめる。そのまま那月が泣き止んでくれるのを待った。
おそろいは気恥ずかしいけど、大切なものという認識が強くなる。
どんな経緯があろうと、それが壊れたときや無くなったときのショックは他のものよりも重くて、那月の場合、自分の半身のように感じているのかもしれなかった。だとしたら、安易におそろいのものを増やしても、いつか那月が傷つくだけかもしれない。突き詰めれば、おそろいのイヤリングとピアスだっていつかは無くしかねないものだ。
もしもの話を考えても仕方ないからと、そこで考えるのを止めることにした。
プレゼントしたときの那月の嬉しそうな顔を忘れなければいい話だと言い聞かせて。
閉園のアナウンスが流れ始めて、パレード後の明るい曲からしっとりとした曲に切り替わる。
そうしたところで、那月がメガネを拭いて掛けなおした。
「…帰るか」
「はい」
携帯電話を仕舞って、今度はちゃんと手を繋ぎながら遊園地の門をくぐった。
ホテルに入る前に那月は目が赤いからと昼間にしていたサングラスを掛けて、チェックインしたときとは違って大人しく俺の1歩後ろに立っていた。
預けていたカードキーをフロントから受け取れば、チェックインしたときに荷物を預かってくれたベルボーイが待機していた。
仕事奪って悪いけど、と初めに添えて、自分たちで勝手に行くから案内はいいと告げれば、ルームサービスは23時までと、朝6時からということ、チェックアウトは10時半までにということを説明される。
「スイートルームなのはすげえけど、なんか落ち着かねえな」
天井や壁が大理石張りで赤い絨毯が敷かれた廊下に苦笑しながら漏らす。
見るからに高級ホテルです、という風情で橙色に光る照明が、夕食を食べたレストランで感じた温かみとは違って、煌びやかで妖しい雰囲気だった。
そして、それを那月はレンみたいだという。
確かにここは神宮寺家が経営しているホテルの一つで、遊園地と雰囲気が違いすぎるせいか、遊園地から少し離れた場所にあった。
この妙な取り合わせの招待券も、シャイニング事務所だからこそ出来るものなのだろうか。
といっても、レンも所属しているし融通が利きやすかったのかもしれないけど。
「ここか…開けるぞ」
俺たちが泊まる部屋の扉にカードキーを通して押し開く。
「どーん!」
入った瞬間に掛け声を出せば、那月はそのまま中に駆け込んでくるくると辺りを見回す。
「わぁ!」
「おお〜〜」
真っ先に飛び込んできたのは部屋の真正面がガラス張りになっていて、11階から見下ろす夜景がとても綺麗だった。
今日は1日よく歩いて走りもしたから、景色を眺めるのを早々に切り上げてソファに腰掛ければふかふかで体が沈みこむ。
あーとか、おーとか、そんな言葉しか出なくて、あちこちを見回る那月からも楽しそうな声ばかりが届いて、少しは元気になったかなと息を吐いた。
「翔ちゃん翔ちゃん見て見て」
「なんだー?」
振り返れば、那月がリビングの隣に続く扉からこっちを覗いて手招きしている。
隣の部屋を見に行くと、俺が想像していた通りの天蓋付きベッドがあった。
「うわっすっげえ!期待を裏切らねえな!マジでイメージ通り!」
サイズはキングかクイーンだか分からないけど、それぐらい大きいものが2つ置いてあった。手だけでベッドのスプリングを押してみると、そこまで沈み込まずちょうどよさそうだった。
「実際こんなん置いてんだなー」
「翔ちゃんもはやく〜」
ごろんと寝転んだ那月が手招きしてきて、飛び込んでしまいたくなるけどぐっと堪える。
「俺、今寝転んだら絶対寝落ちするから先に風呂もらうぞー」
「はぁい」
やけに素直だなと思いながらも、着替えを持って洗面所に行けば、そこもまた豪華で明るい照明が眩しいところだった。壁伝いにある白い洗面台のカウンターに壁一面の鏡。上の棚には綺麗に畳まれたタオルがいくつもあって、小脇にある白いクローゼットにはバスローブが入っていた。
「俺が…これを着んのか…?レンならまだしも…」
那月はどうだろ…砂月なら似合いそうか…?
バスローブを持って鏡の前で自分の体に合わせてみる。
「ねえな…」
あまりの違和感に噴出すよりも呆れが先立った。
カウンターの上にバスローブを放り投げて、タオルを棚から下ろす。
すっかり忘れていた伊達メガネを外して、ピンも取る。
そうしたところで、髪が冷えた汗で湿っていることに気づいた。
「那月〜ってそんなとこで何してんだ?」
リビングへの扉を開けば、那月がいつものメガネを掛けて扉の傍で体育座りをしていた。
「翔ちゃんの声聞きたいなって」
「あーもうお前可愛すぎ」
見上げる那月が嬉しそうに微笑むから、手を取って中に引き込む。
那月の湿った髪に触れて、イヤリングをそっと外してシンクから離れたカウンターの上に置く。
「風邪引いたら厄介だから一緒に入ろうと思ってさ」
Tシャツを脱ぎながら言えば、那月が背中に抱きついてきて、うなじに那月の吐息が掛かる。
「…もう我慢できないよ?」
ちゅっと小さく吸い付かれて、タンクトップの下に那月の手が滑り込んでくる。
「ん……風呂ですんなら…ベッドではなしだからな」
正面の鏡に赤くなった自分の顔が映って、逃げるように反転して那月の服を掴んでかがめさせる。どちらからともなく啄ばむようにちゅっちゅっとキスを交わしながら、那月の力に押されてゆっくりと後退していく。カウンターにぶつかりそこに上体だけ押し倒されて、捲りあげられたタンクトップが頭を通るときキスを遮ってしまう。
そのついでとばかりに上げさせられた腋の下を舐められて体が強く跳ねる。
「っひゃん……くすぐった…んん」
思わず俯いた顔を上げさせられて、深くキスをされる。那月はいつも唇の柔らかさを確かめるように優しくキスをする。でも、今日はいつも以上に舌が絡み付いてきて、キスというよりはただ口を開けさせられているだけのような感覚だった。そのまま舌を重ね合わせれば、痺れで頭が震えてきて目を伏せる。
2人の吐息と早まる鼓動の中に、カチャカチャとベルトを緩める音が響いてくる。
息が絶え絶えで目じりに涙が滲んできて、唾液が口元を伝ってくる。
「んぁ……落ちる…」
ずり落ちそうな体制が辛くて、那月の胸を押し返すと体を持ち上げられて、カウンターの上に座らせられる。
「ここですんの…?」
「お風呂でいっぱいするとのぼせちゃうでしょう?だから…ちょっとだけ、ね?」
那月は嬉しそうに頬にキスをしてきて、いつもの調子、というわけでもなさそうだけど、人の目を気にせず那月を独占できることが嬉しくて、たまには那月の気の済むまで付き合ってやろうと思った。
遠くで何かが聞こえる。潜めるような小さな声。
「…ん……」
傍に居るはずの温もりがなくて、ゆっくりと目を開ける。
途端に頭痛がして眉間を摘むように手を当てた。
「…っつ……な、つきー?」
気だるさを感じながら、目をこすって起き上がる。
そして、その手を退けたとき目に映ったのは、最近やっと見慣れ始めた大きなテレビカメラだった。
「う、うわああ!な、なんだ!?」
「うーん、いい反応するね。おはよう、おチビちゃん」
カメラの奥からちらっと顔を出したのはレンだった。ほかにスタッフらしき人は見当たらない。
「…お、おはよ…じゃなくて!」
「はいはい、それ以上は――」
レンは口元に人差し指を当てて、何も聞くなという。
と、とりあえず、それらしいリアクション…はもうしたのか?
状況を整理しようと僅かに俯けば、自分の格好に気づいて、慌てて布団を肩まで被る。
「わあああ!!もう撮った?撮ってる?」
結局バスローブを着ずに家から持ってきたタンクトップとスウェットで寝てたから、見えるところに痕がついているかもしれない。でも、男らしくないこの行動にしまったとも思った。
「ばっちり」
「レン〜〜〜〜!!」
起き上がろうとして、腰に激痛が走って砕けてしまう。
「おやおや。遊園地ではしゃぎすぎちゃったのかな?」
「うう…」
布団で見えないようにして腰を摩りながら、レンに向かってびしっと指差す。
「くっそーいつかお前にも仕掛けてやるからな!」
「うん。楽しみにしてるよ。あぁ、でも、おチビちゃんには刺激が強すぎるかもしれないね」
「…そういえば、お前って全裸で寝てんだっけ…」
学園時代、レンと同室だった聖川が「朝から最悪なものを見た」とぼやいてたことがある。
レンはインタビューでも答えていたし、周知の事実だ。
「バスローブで寝ることもあるけど、眠っている間にいつの間にか脱げてしまっているよ」
「普通に服を着ろ!服を!」
叫ぶように突っ込めば、レンはカメラを自分に向ける。
「そうだね、全国の子羊ちゃんが添い寝してくれるなら考えるよ。それとも、子羊ちゃんたちは裸のままがいい?」
そして、レンはお決まりのようにウィンクと投げキッスをする。
そのままカメラの電源を落としたレンは、ふうと息を吐いてカメラを下ろすとベッドに腰掛けた。
「本当に重いね、これ」
「おつかれーじゃなくて…寝起きドッキリ無くなったんじゃなかったのかよ!」
「もうやらないと思ってた分、成功したって言えるんじゃないのかな?」
本当なら俺と那月が社長の「節度を守って」という言いつけを守れていれば、企画をなかったことにする必要なんかなかったし、ペナルティが何もないなんておかしいと思っていた。でも、社長は何も言わなかったから聞けなくて。
「それはそうかも、だけど…俺、痕ついてるかもしんねえし」
「俺が見た限りはなかったように思うよ。それに、シノミーには事前に言ってあったからね。いくらシノミーでもそんなヘマしないんじゃないかな」
「そっか…」
のぼせそうになって風呂から出たあと、まだ熱が収まらなくてベッドに誘ったとき、那月はベッドは遠いからって洗面所で続きをした。
砂月は那月に悪いと思ってるのか基本的に後始末をしてくれるけど、那月はあまりせずそのままベッドに雪崩れ込むように寝るから、昨日の那月は俺の体を丁寧に拭いてくれて、服まで着せてくれて珍しいな、とは思っていた。
って、自分で動けなくなるほどやらせるなって話か。
それに那月は痕をつけたがって首筋なんかでも平気でつけるくせに、ほかの人に見せたくないなんて矛盾したことを言うから、最近のマイブームとしてストールをよく使うようにしている。
「つーか、那月はどこに居るんだ」
「薬が切れてたから買いに行くって。それで大丈夫なのかい?頭痛がするんだろう?」
無意識のうちに額に手を当てていたらしく、レンが顔を覗き込んでくる。
「ん…平気。…俺、トイレ……うわっ」
「おっと。フラフラじゃないか」
ベッドから降りて、ふらついて転びそうになったところをレンが支えてくれた。
「…悪い」
「なんなら、そこまでエスコートしようか?お姫様」
レンは俺の手を取って、甲にキスするフリをしてくるから、手を引っ込めるけど振りほどけなかった。
「アホか!誰が姫だ!そういや、あれから絶対女装似合うからしてほしい、とかなんとかいうファンレターが来るようになっちまったんだぞ!」
あれ、というのはもちろん生放送でレンにお姫様抱っこされたことだ。
「そうなんだ。それは悪いことをした、ごめんね。あの時は本当に競技のことを考えてただけで、からかったつもりはなかったんだけど、シノミーにも睨まれちゃったしね。普段あんなにおっとりしてるのに、おチビちゃんが絡むと本当に怖いね」
「那月が怖い?砂月じゃなくて?」
「あぁ…詳しく聞いてないのかい?っとその前にごゆっくり」
いつの間にかトイレの前まで来ていたらしく、レンは俺の手を離すとひらひらと手を振ってリビングに戻っていった。
キザなやつ…。
ああいうのもファンの心を掴むサービスの一つなんだろうけど、それを恥ずかしげもなく素でやってのけるからまたすごい。
「翔ちゃん大丈夫?」
そんなにトイレに篭っていたつもりはなかったけど、リビングに行くといつの間にか帰っていたらしい那月が慌てて駆け寄ってくる。
「お腹痛いよね?僕、中に――」
「アホかァ!レンも居るんだぞ!」
ソファに座っているレンがこっちを見て苦笑している。
「あっ…」
「平気だから気にすんな。ただ薬はくれ」
那月が持っていた頭痛薬と水が入ったペットボトルを受け取って、その場で飲み下す。
「やれやれ。やっとシノミーの信用を取り戻せたかな?って思うと嬉しいけど、その緩んだ気のまま外に行かないでほしいね」
レンの隣に腰掛ければ、間に俺をはさむように那月が腰掛ける。
「…順を追って説明すると、初めに俺がカメラを持っておチビちゃんの家に潜入したときのことになるのかな」
そう言って、レンは説明を始めた。
レンが寝起きドッキリ企画で俺の部屋に行ったとき、俺の部屋には那月のものがいっぱいあるから見たことなかったら当然だけど、俺が本当は可愛い物好きなのを隠してたんじゃないかと思ったらしい。同時に那月のことも薄っすら頭には浮かんでたらしいけど、リビング程度じゃ確信が持てなくてそのまま小声で実況しつつベッドルームへ。
そこで最初に目に飛び込んできたのは俺が那月に抱きしめられる形で寝てたこと、辺りを見回して当たり前のようにある那月の私服やパジャマ、ぬいぐるみに辛口レシピが多く載っている料理本の数々…それらを確認してどうしたもんかと思っていたら、那月が飛び起きてレンに掴みかかったらしい。
「シノミーはとても耳が良いみたいでね…」
「初めは泥棒さんだと思ったんです。でも、レンくんの声だったし…真っ直ぐ寝室に来たから…その…」
「俺をおチビちゃんの浮気相手だと思ったんだよね」
「はぁ!?お前俺を疑って――」
「違います!無理やり迫られてるんじゃないかって思っただけです!!」
「…酷いなぁ」
レンが苦笑すると、那月が申し訳なさそうに肩を縮めた。
「その時はレンくんがテレビカメラを持ってたから冷静になれたんですけど…」
「俺が生放送でおチビちゃんをお姫様抱っこしちゃったからね…また勘違いされてしまったわけさ」
「はぁ…レン相手じゃなくても、男に迫られてるって思われるだけでもショックだっつーの。そんなに俺は男らしくないか?」
「そういうことじゃないんだよ。例えばシノミーみたいに、小さくて可愛らしいおチビちゃんが男らしく在ろうとする…そのギャップに惹かれるという男がいるかもしれないからね」
「小さくて可愛いって言うな!」と途中で横槍を入れれば、那月が「本当に小さくて可愛いです!」って抱きしめてくる。
実際それで悩んだこともなくはなかったんだけどな…。
俺の身長が元から高かったり、今より伸びたりしたら那月はどうなるんだろうって。でも、いつか身長だけじゃなくて何かが原因で那月が俺を恋愛対象として好きじゃなくなったとしたら、それでも俺は友人として那月の傍に居続けるって砂月に誓った。例え那月に嫌われてそうなったとしても、砂月に那月の前から消えろって言われない限り、俺はそうすると決めている。
「本当にレンくんは翔ちゃんをそういう対象として見てないんですよね?」
「やけに疑り深いね。俺にそっちの趣向はないし、そもそも略奪愛は好きじゃないんだ。直前まで愛していた人が居るのに、コロっと俺になびかれても虚しいだけだって知っているからね」
「モテる男は言うことが違うな」
「…真実の愛はどこにあるのかと思ってしまうのさ。それに今はもうちょっかいかけて揺らがないか、確かめようなんてことはしないようにしてるんだ。幸せそうなカップルを見るだけで微笑ましいものだからね。…さて、どこまで話したかな」
何があったんだと聞きたくなるけど、興味本位で聞くのもどうかと思って黙り込む。
そして、レンは話を続けた。
企画を無かったことにしてもらおうと社長に話をつけようとしたところで、企画自体がレンに対するテストだったということだった。
そんな遊ぶみたいに俺たちの関係をバラすのもどうかと思うが、確かに寝起きドッキリという企画上、部屋の鍵も必要だし社長の許可が要るとは思っていた。実際に俺たちにペナルティがないこともあって、余計に納得せざるを得なかった。
「つまり、ボスはおチビちゃんとシノミーの関係の危うさについて危惧していたってわけだ。それで、君たちのサポートをする人間にこの俺が選ばれた」
それに社長はありのままの俺たちの様子も映像で確かめたかったらしい。
「まぁ、誕生日だからって生放送がある前日にやることやっていたら、流石にボスもペナルティを与えていたかもしれないね」
「あ、あっぶねー…」
「僕たちのためにたくさん動いてくれたのに、何回も疑ってごめんなさい…」
レンは企画を一つ潰すことになるわけだから、その企画がなくても放送を盛り上げさせるための景品の手配を手早く済ませていたんだとか。
「元はといえばボスがテストなんかしなければ疑われるようなこともなかったんだし、あの時はシノミーだってすぐに誤解を解いて、俺を信用してくれたからこそ説得という名の合格を手に入れられたんだ。それに恋に嫉妬は付き物だからね…気にすることじゃない。あぁ、でも、虫がつかないようにって思う気持ちは分かるけど、おチビちゃんに誰かが迫るたびに目くじら立ててたらあっという間にバレてしまうよ」
「…悪いな、レン。サポートなんかやらせることになっちまって…。それなりに平和に過ごせてたから、そこまで考えてなくてさ…マジで助かる。出来るだけ、迷惑掛けないようにするから」
「うん。サポートといっても多少のフォロー程度で、必要以上に干渉するつもりはないから、そこは安心してほしいな」
レンはそう言って那月にウィンクを飛ばす。
どうやら誤解が解けてもレンは那月が怖いらしい。
一体、俺が見てないときに何があったのか…。
すっとレンが立ち上がって廊下の扉に向かう。
そして、思い出したように振り返って言った。
「あぁ、相談事があるならいつでも乗るよ。…ただ、俺がシノミーに殺されない程度にしてほしいな」
「大事なお友達にそんなことするわけないですよぉ」
「…だと嬉しいね」
最後にレンはテレビカメラはそのままにしていていいよ、とだけ言って部屋を出て行った。
一気に説明されて、どっと疲れた気がした。
「…つーか、寝起きドッキリ自体がレンのテストだったんなら、ここでまたやる必要なかったんじゃねえの?」
「僕も翔ちゃんの寝起きをみんなに見せたくないなぁって思ってたんですけど、ほかの局でこういう企画が上がったときに僕も知らされないまま撮られちゃう可能性あるから、早めに事務所主導でやっておく方がいいってレンくんが」
「なるほどな…。寝起きドッキリなんてそう何度もやる企画じゃないもんな。1度やってしまえば、数年は安心か」
「うん…」
「お前は撮ったのか?静かだった気がするけど」
「ちゃあんと撮りましたよぉ。実はこのお休みは僕たちのマネージャーさんたちにとっては寝起きドッキリのお仕事、ということになってるんです。お休みがなかなか取れないってレンくんに相談したら、お仕事として僕たちのスケジュールに入れるよう頼んでくれて」
「お、おお…」
マネージャーに連休を合わせて欲しいって頼んだのは6月中ごろを過ぎた辺りだったのに、合同ライブにミュージカルとお互い忙しくて、連休ともなるとなかなか調整はされなかった。
そして、突然スケジュールに2連休が出来ていて、初めは単純に那月のミュージカルが一段楽したからだと思ってたんだけど、8月は8月で那月は単独ライブがあって曲作りをする時間も必要だから、どこにそんな余裕が…とは思っていた。
「景品といい、どの辺がフォロー程度なんだか…」
那月に手を引っ張られて、顔を見れば悲しそうな顔をしている。
「…翔ちゃん、レンくんに惚れちゃった?」
「なんでそうなるんだ、よ」
額を小突いてやれば、体を抱き上げられて向かい合わせにして那月の膝に乗せられる。
髪を撫でて後ろに掻き揚げてやれば、くすぐったそうにしながら那月が俺の手に擦り寄ってくる。
髪の下から覗く那月の耳のムーンストーンが光って、まだ気恥ずかしくて見慣れないそれに触れる。
――僕たちの愛がずっと続いて幸せだって、未来を教えてもらってるみたい――
ムーンストーンをプレゼントしたとき那月が言った言葉が蘇る。
「……嫉妬なんかする必要ないだろ」
イヤリングに触れる俺の手にそっと手を重ねられる。
「それってずっと僕と居てくれるってこと?」
遊園地ではぐれてしまったことで、より強く那月の傍に居たいと思った。
眠る前の幸せを思い出せば、この距離だって遠く感じてしまう。それぐらい。
「…一時だって離れたくねえよ」
そして、那月の額にキスをする。
「ぼ、ぼくいま、すっごくきゅううんって!!」
折角かっこよくキメられたと思ったのにこいつは…!!
照れが一気に来て、思わず俯けば、髪にキスを落とされて、ちゅっちゅとうなじに移動していく。
熱くなってくる耳を触られて、肩をびくつかせてしまう。
「かわいい、かわいい翔ちゃん…」
「うっせ…」
「ね、ちゅーしよう?翔ちゃん」
たまには俺だって意地悪してもいいだろ?って黙って俯いていたら、そっと抱きしめられる。
耳元に那月の吐息が掛かって、甘く甘く囁かれる。
「…だいすき」
それだけで意地悪しようなんて気がどっかいってしまったから、強く抱きしめ返した。
「それはたぶん、砂月は携帯が壊れたことを悲しがったわけじゃなくって、お前を抱きしめてやれなくて悔しかったんだと思うぞ」
「え、そうなの…?」
『それ以外に何があるんだ…?機械なんかより那月の方が大事だからな』
「……っ!翔ちゃん、さっちゃんを抱きしめて!」
「な、なんだよ…?」
「はやく!」
「ったく、しゃーねえなー…これでいいのか?」
「ぎゅ〜〜〜!!」
「くるしっ、やめ…!!」
「翔ちゃんもさっちゃんもだーいすきです!!」
「…わ、わかった、わかったって、ちょっと緩めろ…!」
『ふっ……俺はお前らが幸せならそれでいい』
fin.
<< 前編
-----
長い〜〜!!
迷走に迷走を重ねて、ボツカットだけで1万文字突破するという事態に()
書きたかったことは書けたかな?たぶん!
翔ちゃんの男らしさというものを考える日々で、逆になっちゃんが乙女化した?ようなそんな気がする。
ちくしょう那翔ちゃんは何でもかわいいってことだよ。知ってた!!
執筆2012/06/12〜21
以下、おまけ。

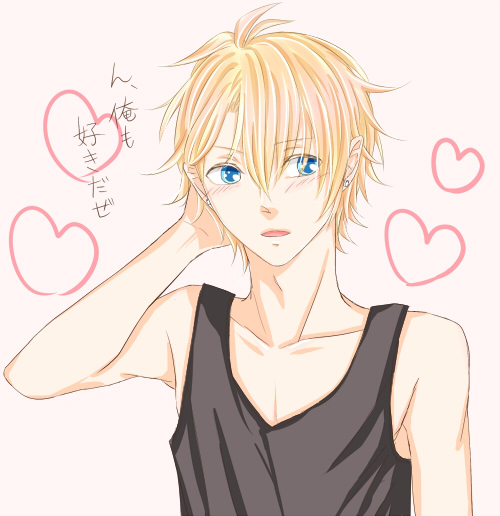
えんだああああああお前らマジ結婚しる!
21歳のなっちゃんは髪がちょい長いイメージです。
19歳の翔ちゃんは相変わらずです。でも、なっちゃんのおかげでちょっと色気出てたらいいなって思います。
※前編の方にあったおまけ絵は撤去しますた!
2012/06/22